出産•育児に関する制度
出産
産前から出産、産後にかけて利用できる制度です。出産する女性職員のほか、出産する妻がいる男性職員が利用できる制度もあります。
休暇制度
| 産前休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 有給 |
| 対象 | 分娩予定日から起算して6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性職員 |
| 期間 | 申し出た日から出産の日まで |
| 備考 | 出産の日が分娩予定日より前後した場合は、出産の日までの期間が産前休暇として取り扱われます。 |
| 産後休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 有給 |
| 対象 | 出産した女性職員 |
| 期間 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまで |
| 日数 | 出産後6週間を経過し、医師が就業に支障がないと認めた場合は、申し出により勤務することが可能です。 |
◎育児休業の個別周知•意向確認について
職員自身が妊娠したり、配偶者が出産したりする場合は、ご自身が所属する部局等の総務担当へ申し出てください。申出があった場合は、育児休業制度等を周知し、育休の取得意向を確認いたします。
| 妻の出産休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 有給 |
| 内容 | 妻が出産のため入院した日から産後2週間経過するまでの間に、妻の入退院の付き添いや出産時の付き添い、入院中の世話、産まれた子どもの出生の届出等の際に取得できます。 |
| 対象 | 妻が出産予定または出産した男性職員 |
| 日数 | 2日の範囲内の期間 |
◎妊娠•出産時は、市役所等への手続きを忘れずに!
| 時期 | 申請事項 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 妊娠したら | 母子健康手帳 (母子手帳) |
健康保険証、妊娠届出書 |
| 妊婦一般健康 診査費用助成 |
母子健康手帳申請時に母子保健のしおり(妊婦一般健康診査受診票)とセットで交付 | |
| 妊産婦医療費等 助成 (津市の場合) |
健康保険証、印鑑、預金通帳、市所定の用紙による医師の証明 | |
| 出産したら | 出生届 | 届出書(医師の証明記載のもの)、届人の印鑑、国民健康保険証(父または母が加入している場合) |
| 子ども 医療費助成 |
子の健康保険証、印鑑、預金通帳、住民税所得課税証明書 | |
| 児童手当 | 請求者の預金通帳•健康保険証写、年金加入証明書、所得課税証明書 |
※制度手続の方法は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの地域の市役所等にお問い合わせください。
◎出産費•家族出産費または出産育児一時金について
組合員またはその家族が出産した場合は、文部科学省共済組合(以下「共済組合」といいます。)から1児につき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48万8千円)が、出産費•家族出産費または出産育児一時金(以下「出産費等」といいます。)として支給されます。
■出産費等の医療機関等への直接支払制度
直接支払制度とは、医療機関が被保険者等に代わって共済組合に出産費等の申請を行い、直接、出産費等の支給を受けることができる制度です。出産費等の支給が直接医療機関等へ支払われることから、医療機関等の窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。なお、出産費用の額と出産費等の額に差額が生じた場合は、以下のとおりです。
●出産費用が50万円を上回った場合
上回った差額分を、窓口で支払っていただくことになります。
●出産費用が50万円未満の場合
大学所定の出産費請求書•領収書•直接支払制度の合意書の写しを企画総務部人事労務チーム福祉担当に提出することで、差額分が支給されます。
●出産費等の医療機関等への直接支払制度を利用しない場合
窓口での支払いの際、現金で一時的に全額負担していただきます。後日、大学所定の出産費請求書•領収書•直接支払制度合意書の写しを企画総務部人事労務チーム福祉担当へ提出することで、出産費等が支給されます。
※出産費•家族出産費とは別に、組合員またはその家族が出産した場合は、出産費附加金として4万円が支給されます。(請求される場合は、「出産費、家族出産費請求書」を企画総務部人事労務チーム福祉担当へ提出してください。)
■リスクを伴う出産について
限度額適用認定証の手続をすると、高額入院費の負担軽減となります。
育児
子育て(育児)期に利用できる制度として、育児休業や短時間勤務、各種休暇等の制度が整備されています。男性職員も積極的に利用しましょう。
休業関係諸制度
| 出生時育児休業 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 無給 | 無給 |
| 内容 | 職員が産まれた直後の子を養育するために休業することができます。 対象は主に男性労働者ですが、養育する子が養子の場合等は女性も取得できます。 |
| 期間 | 子の出生後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間 |
| 回数 | 分割して2回取得可能(まとめて申し出ることが必要) |
| 備考 | 有期契約労働者の方は、申出時点で、出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合取得できます。 |
| 育児休業 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 無給 | 無給 |
| 内容 | 職員が子を養育するために休業することができます。 取得する者の性別や、養育する子が実子であるか養子であるかは問いません。 |
| 期間 | 子が出生した日から3歳に達する日(誕生日の前日)までの期間 ※期間を定めて雇用される職員(職員の任期に関する規程に基づき雇用される職員を除きます。) 及び無期労働契約転換者ついては1歳に達する日までの期間」 |
| 回数 | 分割して2回取得可能 |
| 備考 | 継続雇用された期間が6月未満の職員、申出の日から1年以内に雇用関係が終了する職員、1週の所定勤務日数が2日以下の職員は利用できません。 |
| 部分休業 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 無給 | 無給 |
| 内容 | 1日を通じて2時間を超えない範囲で、託児や通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位で休業することができます。 |
| 期間 | 子が出生した日から小学3年生終了時までの期間 |
| 備考 | 継続雇用された期間が6月未満の職員、1週の所定勤務日数が2日以下の職員、また、パートタイム職員にあっては1日の勤務時間が6時間以下の日は利用できません。 |
| 利用できる回数の制限はありません。 |
| 育児短時間勤務 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 無給 | 無給 |
| 内容 | 子を養育するため、次の①~③のすべてに該当する形態で勤務することができる制度です。 ①1日の勤務時間は7時間45分以下(医学部附属病院看護部に勤務する職員にあっては、1回の勤務時間は15時間30分以下) ②1週間の勤務時間は20時間以上 ③4週間を単位とし、各週の勤務形態は同一 |
| 期間 | 子が出生した日から小学3年生終了時までの期間 |
| 備考 | パートタイム職員、国立大学法人三重大学職員の任期に関する規程第2条第2号から第5号までの規定で雇用された職員、継続雇用された期間が6月未満の職員は利用できません。また、利用できる回数の制限はありません。 |
◎育児時短休業中に受けられる手当金等
●育児時短就業給付金(雇用保険)
2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。
◎育児休業中に受けられる手当金等
育児休業により勤務しない日については、大学からの給与は支給されませんが、所定の手続きを行うことで共済組合や雇用保険から、手当金や給付金を受給することができます。
●育児休業給付金(雇用保険)
育児休業に係る子が1歳に達するまでの期間(※1)に、賃金月額の50%(※2)が支給されます。
●育児休業手当金(共済組合)
育児休業に係る子が1歳に達するまでの期間(※1)に、給付期間1日につき標準報酬日額の50%(※2)が支給されます。
(雇用保険による育児休業給付金の支給を受けるときは、支給されません。)
●出生後休業支援給付金(雇用保険)
子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に13%相当額を上乗せして、最大28日分の給付金が支給されます。
※1:夫婦ともに育児休業を利用した場合は、 1歳2ヶ月まで、子が1歳以降も保育所に入所できない場合は最長2歳まで支給されます。
※2:育児休業の開始日から180日目までは、67%となり、181日目以降は50%が支給されます。
休暇制度
| 育児参加休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 有給 |
| 内容 | 妻が出産する場合で、当該出産にかかる子または小学校就学前の子を養育する際に取得できます。 |
| 対象 | 妻が6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定または出産後1年以内の男性職員 |
| 日数 | 5日の範囲内の期間 |
| 保育休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 無給 |
| 内容 | 子どもへの授乳や託児所への送迎等を行う際に取得できます。 |
| 対象 | 生後1年に達しない子を育てる職員 |
| 備考 | 1日2回•1回につき30分(男性職員については、妻が同日に同種の制度を利用した場合は、妻が利用した期間を差し引いた期間) |
| 子の看護休暇 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 有給 | 無給 |
| 内容 |
子どもの看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせること、感染症に伴う学級閉鎖等又は入園(入学)式及び卒園式への出席)を行う際に取得できます。 |
| 対象 | 満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を養育する職員 |
| 備考 | ーの年(非常勤職員についてはーの年度)において5日(養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
勤務時間の弾力化
| 深夜勤務の免除 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
| 内容 | 申し出により、深夜帯(午後10時から午前5時まで)の勤務が免除されます。 |
| 対象 | 小学校就学前の子を養育する職員 |
| 時間外勤務等の免除 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
| 内容 | 申し出により、時間外勤務や週休日等における勤務が免除されます。 |
| 対象 | 小学校就学前の子を養育する職員 |
| 時間外勤務の制限 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
| 内容 | 申し出により、1ヶ月24時間•1年150時間までに制限されます。 |
| 対象 | 小学校就学前の子を養育する職員等 |
| 早出遅出勤務 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
| 内容 | 申し出により、始業終業時刻をあらかじめ定められた時刻で勤務することができます。 |
| 対象 | ①小学校就学前の子を養育する職員等 ②小学校に就学している子のある職員のうち、学童保育所等に送迎を行う必要がある職員 |
◎「三重大学さつき保育園」について
「三重大学さつき保育園」は、三重大学で働く教職員の子どもたちが通う施設です。月極保育のほか、一時預かり、病児保育にも対応しています。さつき保育園は医学部附属病院の敷地内にあります。



●さつき保育園についての問い合わせ
[入園選考について]
医学•病院管理部総務課総務係
(TEL:059-231-5428/内線6014)
[入園後について]
ダイバーシティ•インクルージョン推進室
(TEL:059-231-9830/内線9830)
◎「三重大学医学部附属病院 学童保育所さくら組」について
「学童保育所 さくら組」は、医学部及び附属病院で働く教職員の子育てを支援するための施設です。小学生のお子様を放課後や夏休み等にお預かりしています。
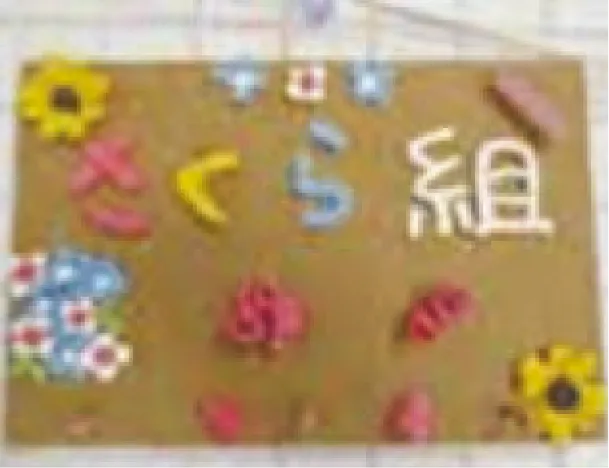

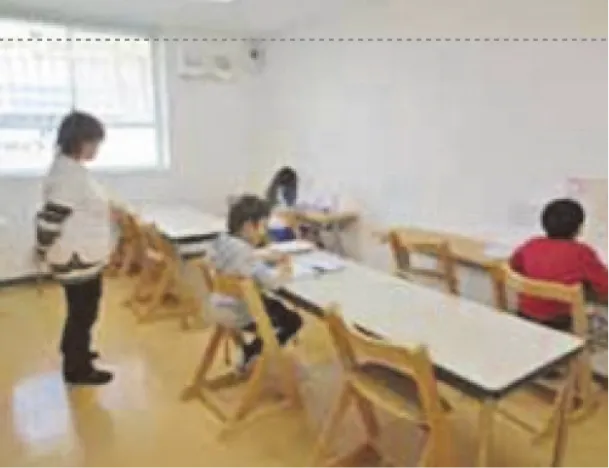
●学童保育所さくら組についての問い合わせ
医学•病院管理部総務課
(TEL:059-231-5240/内線6318)
在宅勤務制度
| 在宅勤務 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 〇 | 〇 |
| 内容 | 職員の自宅その他自宅に準ずる場所(以下「自宅等」という。)において情報通信機器を利用し業務を行うことができます。 |
| 対象 | 小学校3年生までの子を養育している職員(その他、自宅勤務を実施する職員の業務内容等を勘案し、在宅勤務を行うことが適正と判断される者、自宅での業務が円滑に遂行できると認められる者、自宅等の執務環境、情報通信環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者、在宅勤務により、業務の生産性、効率性の向上等が見込まれる者、在宅勤務の実施により、職場全体や学内外との対応を含め業務の遂行に影響を及ぼさない者等の要件を満たす場合は、許可を受けて行うことができます。) |
| 備考 |
必要と認められる実施頻度 |
◎長期休業後の復職について
育児休業や介護休業等により長期にわたって仕事を離れると、復職するにあたって不安が生じることもあります。そんなときは1人で悩まず、上司等に相談してください。また、保健管理センターにおいても、こころとからだの健康相談(予約制)を行っています。